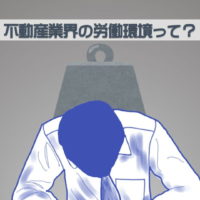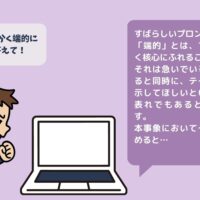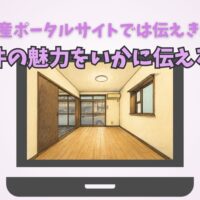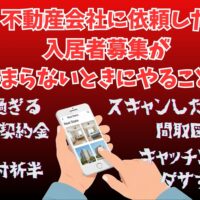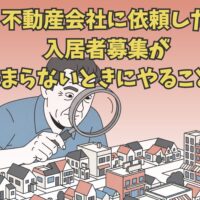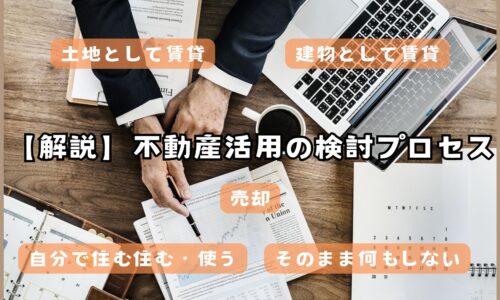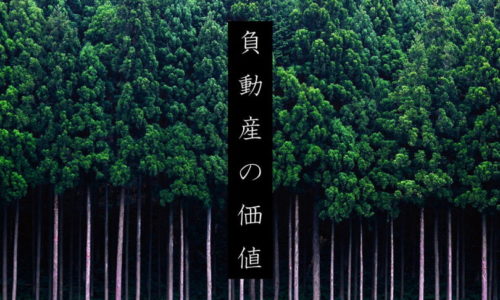所有物件の入居者の死に際し、役所の対応に抗う私の体験記【全3回/中編】
家主による死亡届を拒む役所
家主には死亡届の義務がある
Oさんは死亡届が出されておらず、戸籍上はまだ亡くなったことになっていませんでした。
戸籍法には下記のように記載されています。
戸籍法 第86条
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
同 第87条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
亡くなった方の関係者が死亡届を出さないでいると、行政機関は死亡者を把握できず、住民や国民の数がわからなくなり、まともな予算を組めなくなります。また、死者に年金が払われ続けたりします。実際、年金を頼りに生活している親族が死亡届を出さず、何年間も不正受給を続けたケースがニュースになったりしています。戸籍法で死亡届の提出を義務としているのはそういったことを防ぐ趣旨です。
そして、家主である私は第三順位の届出義務者で、死亡してから1ヶ月以上、私が知ってからもその時点で7日以上経過しているので、義務を怠っており、直ちに義務を履行しなければならない立場となります。
そこで、私はそのまま戸籍住民課の担当窓口で死亡届の手続きをしようとしました。
しかし、
その窓口では死亡診断書がないと死亡届は受理できないと言われました。
もちろん、私は死に立ち会っても、葬儀に出席してもいないので死亡診断書は持っていません。
死亡診断書を出さない障害高齢課

死亡診断書を持っているのは、葬儀を行なった障害高齢課でしょう。
私は今度は2階に行き、障害高齢課で死亡診断書について伺いました。窓口は先日のKさんです。
「死亡診断書は障害高齢課にありますが、あなたにお出しすることはできません。」
それなら、障害高齢課で速やかに死亡届を出すように言いました。
「葬儀はしましたが、相続人の調査がまだなので、火葬はしていません。死亡届の提出はその後になります」
役所の語る調査は民間の感覚からするとたいていは非常にゆっくりです。というか、調査といっても何もしないで関係者からの連絡待ちをすることもしばしばです。
しかも、火葬をしていないということは遺体は腐敗を防ぐために葬儀社の冷暗所に入れられています。それだと、葬儀社によりますが一般的には1日5000円〜10000円の費用が掛かります。
せっかくOさんにはそこそこの預金がありソフトランディングできそうなのに、期間が掛かるほどに、私が相続人に請求する賃料が増え、さらに冷暗所の費用が掛かるのです。債権者同士がかち合って債権額が預金額を超えるとお互い取りっぱぐれが生じます。
その預金だってそのままの保証はありません。90歳超のOさんは自分で入出金せず、誰かに頼んでいた可能性は大いにあり、その人がすでに着服しているかもしれません。
(ちなみに私が金融機関に出向きOさんの口座を凍結することはできましたが、その時点では毎月の賃料を自動振込している可能性があったので手続きをせずにいました。後日、自動振込していないことを確認した後に金融機関に凍結の手続きを行なっています)
すべての要素が時間が経つほどに解決が遠のきます。
なぜ、障害高齢課はそこまでして死亡届を出し渋るのでしょうか。
一つ考えられるのは相続人からの苦情を恐れていることです。
近年は高齢化と単身世帯の増加が同時に起きており、身寄りのない方が亡くなるケースが増え、全国の市町村の担当部署の業務量は増加していると思われます。その中で、起きている社会問題の一つに、身寄りのない人だと思って火葬したら、後に相続人が判明し揉めることがあります。NHKでも特集され、海外から戻ったら親が遺骨になっていたと当事者が涙ながらに訴えていました。確かにそれは青天の霹靂で、連絡一つも寄越さない役所に苦情を言いたくなる気持ちはわかります。
対して、また別の問題もあります。2024年6月に名古屋市で身寄りのない2人の遺体に関する事務処理を怠り、葬祭業者の保冷庫に2年以上放置し火葬されないままにしたとして、担当職員が減給処分となりました。(この時点ではまだ公表されていませんでしたが)
苦情を恐れるのはわかりますが、放置するデメリットもありますし、戸籍法の義務を果たさなくていい程の理由にならないように思います。
私はKさんに突っ込んで聞きました。
「私は家主として死亡届を出す法的な義務を負っています。そちらが死亡診断書を持ったままでいることでその義務を果たせません。障害高齢課としても、死亡の事実を知り、死亡届を出せる状態にありながらそれをしないのは戸籍法の趣旨に反しますが、どういった根拠でそういう判断をしているのですか?」
Kさんはいつもの傾聴モードから明らかに態度が変わりました。いい加減にしろという怒気が感じられます。
「墓地埋葬法です!」
墓地埋葬法は、埋葬や火葬、墓地の設置・管理等について定めたもので正確には墓地、埋葬等に関する法律ですが、そのときの私は墓地埋葬法の言葉自体が初耳で、正直言って怯みましたが、それを押し隠すように強気で聞きました。
「墓地埋葬法の何条ですか?」
「…。ちょっと待ってください」
Kさんも答えられません。確認のため一度奥に引っ込みました。チキンゲームが功を奏したのかもしれません。
Kさんは戻ってくると、
「9条です」
墓地、埋葬等に関する法律 第9条
死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
障害高齢課がOさんの死亡手続きを主導する根拠であるのは確かですが、相続人調査が終わるまで火葬してはならないとも、それまで死亡届は出してならないとも、他の関係者に死亡診断書を引き渡してはならないとも書いていません。
それを突っ込むと、
「規程に従っているのです!」
墓地埋葬法9条における市町村の責務を果たすために各市町村は具体的な手順を規程に定めているのでしょう。そして、これは推測ですが、宮城野区障害高齢課の規程では、相続人調査、その後の火葬、さらにその後の死亡届の順に書いていて、例外的なバリエーションがないか、あっても乏しいのでしょう。
しかし、規程は役所内部のルールに過ぎず、対外的に規程を理由に役所の判断を正当化できません。規程が他の法律に趣旨に反しているときはなおさらです。
それを指摘すると再度奥に引っ込んだ後に、
「保健福祉センターの判断です!」
保健福祉センターは障害高齢課の上位の組織です。(私はこの時点では知りませんでしたが)
「だから、保健福祉センターはどの法律を根拠にそう判断したのですか?」
「法律ではありません。保健福祉センターがそう判断したのです!」
Kさんは強い口調で言い切りました。これで話は終わりだと言わんばかりです。
もちろん私はこんな返答に納得いくわけありません。法律なんか関係ないと堂々断言する自治体職員がいることが驚天動地ですが、Kさんは悪びた様子ではなく、むしろ、Kさんには私が己の利益のために手段を選ばず書類の引き渡しを迫ってくる悪徳業者と見えているようです。
この極度の温度差は何でしょうか。
死亡届を受理しない戸籍住民課

障害高齢課との交渉は決裂しましたが、一つだけ私には希望が残っていました。
戸籍法86条には続きがあります。
戸籍法 第86条3項
やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。
私は再度1階戸籍住民課に行きました。
窓口に立った老齢の担当者に戸籍法の86条3項をもとに死亡診断書なしでの死亡届に応じるよう求めました。
しかし、担当者は応じられないと言います。理由を尋ねると、
「それは規程にありません」
またです。もちろん私は引き下がりません。
「法律に記載されているのに、実業務にそれを反映させずに道を塞いでいるのは自治体として手落ちではないでしょうか?」
「そんなこと私に言われても…」
所詮は窓口です。
私は腹が立ってさらに尋ねました。
「行政の怠慢により亡くなった方に年金が払われ続けます。もちろん死亡した後の分は返納の対象にはなりますが、回収できなくなったり、場合によって、その年金を着服する不届な輩が出る可能性もあります。市民から預かった公金を扱う立場として、このことをどう考えますか?」
担当者は今度は強い口調で言い切りました。
「やむをえないことだと考えます」
自治体職員と法律

Kさんと、戸籍住民課の老齢の担当者、二人の対応を突き合わせて考えると役所の考え方がよくわかります。
Kさんは福祉事務所の判断としていますが、それは福祉事務所が恣意的に匙加減で判断しているということではなく、そういう規程であり、戸籍住民課の老齢担当者が死亡診断書なしでの死亡届を受理しないのも規程です。
規程は業務マニュアルのようなもので、彼らのような自治体職員は法律より、要綱・要領・規程といった役所の内部ルールを向いて仕事をしているのです。
そもそも法律をもとに、具体的な手順、詳細を定めたものが規程ですが、時間の経過とともに法律と距離ができてしまったり、一部条項が規程に盛り込まれていない場合がありますが、彼らのような現場の職員はいちいち法律と内部ルールの整合性をチェックしていたら仕事がまわりません。
実際、法律は曖昧なことばかり書いていて、ザル法もあり、中には国会議員のパフォーマンスの産物のような中身のない法律まであります。
市町村には立法権がないので、法律は市町村にとっては無条件に上から降ってきますが、自治体職員にとっては頻繁な法律の改正や、突如飛んでくるような国の指示(政権の人気取りのために給付金を配るとか)に振り回されず、目の前の業務を行いたいとの思いもあるのかもしれません。実際に市民生活にまつわる具体的な業務を担っているのは国よりもむしろ断然に市町村で、自治体職員には自分たちのお陰で成り立っていているという自負もあると想像します。
しかし、ほとんどの市民は自治体職員の市民ファーストな姿に心打たれて従っているのではありません。
彼らに徴税権や許認可権があるからです。
そして、徴税権や許認可権はいずれも国が定めた法律を根拠としており、自治体はそれにより権限を行使できます。
徴税権や許認可権は行使し、公金の扱いはその原資が市民の税でも自治体に100%判断権があると窓口の職員まですべからく徹底されている一方、法律よりも規程が優先だと強弁するようでは、区役所に来て、税金は払いたくないけど、行政サービスは受けたいと駄々をこねる困った市民と何が違うと言うのでしょうか。
(【全3回/後編】に続く)
*故人のプライバシーに係る記載がありますが、故人に対しては個人情報保護の対象外となります。なお、Oさんに相続人はなく、相続財産管理人手続きも終了しています。ただし、Oさんのプライバシーを明かすことは記事の目的ではないので実名は伏せています。
*役所が私に行った対応は、役所において公然と判断したことであり、担当者名を含め、私に守秘義務はありません。ただし、私には職員個人を批判する意図は一切ないので実名は伏せています。
*なるべく事実に即して記載するよう努めていますが、記憶が曖昧なところもあり、大意を曲げない範囲で想像で補って記載しています。
shiro-shita
最新記事 by shiro-shita (全て見る)
- AIが賢くならない未来 - 2025年12月13日
- 不動産ポータルサイトでは伝えきれない物件の魅力をいかに伝えるか - 2025年12月4日
- 不動産会社に依頼した入居者募集が決まらないときにやること 不動産オーナーによる物件マーケティング戦略の検証その2 - 2025年11月27日