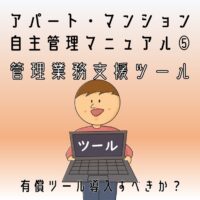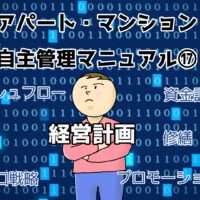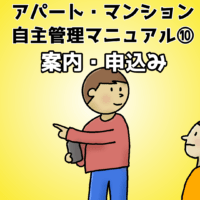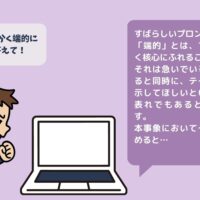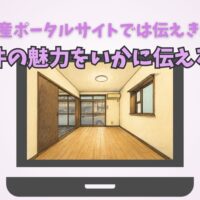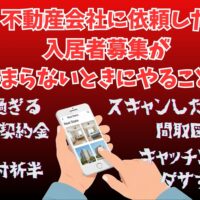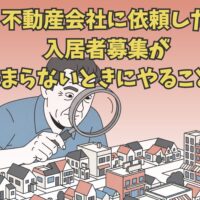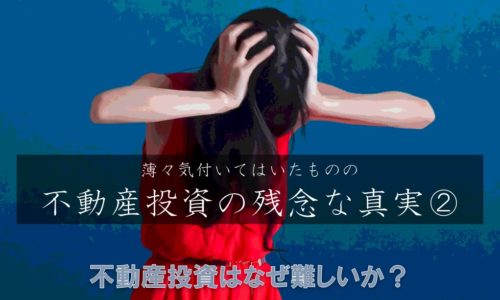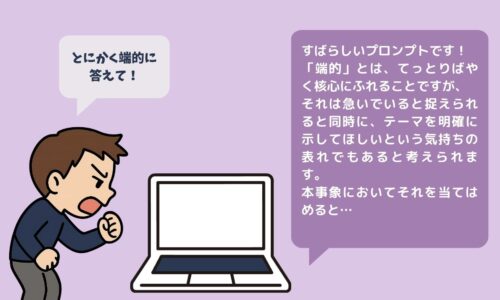Contents
不動産賃貸経営に欠かせないリフォーム費用の考え方とは?
賃貸不動産経営を行なう上でリペア・バリューアップといったリフォーム費用は常に付きまとう問題ですが、
あまりに日常ごとなので何となく高額でなければいいやくらいで判断してしまいがちで、その出費が本当に効果的なのか検討することは案外少ないかもしれません。
余裕綽々で賃貸経営しているのであれば「常に最良のコンデションを目指して!」みたいなスタンスでいいのかもしれませんが、
かなり厳密に費用対効果を追求しないと利益を出せない物件もありますし、今後の不動産賃貸業の厳しい経営環境を考えると、例えこれまでは余裕綽々だったとしても、より生きたお金の使い方になるようコスパの検証をすべきです。
それで…
リフォーム費用のコスパ検証ってどうすればいいでしょうか?
こんな風にコスパ検証してませんか?…
現時点で不動産業界において賃貸不動産のリフォームのコスパを検証する確立された基準はありません(多分)。
各々が自分なりにやっていると思いますが、中でもよくあるのは、
部屋をリフォームして貸し出す場合
リフォーム費用:120万円
リフォーム後の賃料:5万円
120万円÷5万円=24ヶ月(2年)
2年で退去されると原状回復工事が必要なのでその分と合わせると赤字になる、悩ましい…
みたいな。
しかし、その考え方からすると、リフォームをしないで家賃下げて3万円で貸すことができれば効果は無限です(0円÷3万円)。
コストと収益を対比している訳ですが、そもそもリフォームは不具合を直したり予防するために行う面が大きいので必ずしも収益に直結する訳ではありません。
なら、なるべくリフォームはしない方がいいのでしょうか?
それは違うと直感的にわかりますが、どのように論理的に説明すればいいでしょうか?
コスパ検証こうしてみては!
一口にリフォームといっても、新たに貸し出すための原状回復工事と、不具合を直すための修繕工事では目的が違うので同じ土俵で比較するのは適切ではないでしょう。
また、検証といってもこの数値を上回ればみたいな絶対的基準値を設定するのは難しいと思います。各物件ごとに状況が違いますから。
あくまでも当該物件においてとりうる選択肢の中で最良を特定する手法として各選択肢を相互的に比較するのが適当ではないかと私は思います。
具体的ケースで考えてみましょう。
リフォームしないと貸せない空室をどうするか
お風呂が壊れてユニットバス丸々交換しないと貸すことができないというケースを考えてみましょう。
選択肢(1) ユニットバスを交換して貸し出す
リフォーム費用:70万円
想定賃料:5万円
想定稼働率:90%
選択肢(2) そのまま何もしない
費用:0円
想定稼働率:0%

物件のその後の使用年数が長ければ長いほどリフォームした方が有利となりますが、想定賃料&稼働率が低いと物件の寿命が先に来る場合があります。
通常の原状回復とバリューアップのリフォームプランを比較する
設備の入れ替えを行ってバリューアップした方がいいか、壁紙や畳表替の表層部分のリフォームで済ませるべきか判断する場合
選択肢(1) 設備の入れ替え
リフォーム費用:100万円
想定賃料:5万円
想定稼働率:90%
選択肢(2) 表層リフォーム
リフォーム費用:10万円
想定賃料:4万円
想定稼働率:75%

やはり物件の使用年数が長ければ長いほどバリューアップした方が有利となりますが、賃料・稼働率次第となります。
もう一つの選択肢である何もしないを含めて検討し総合的に判断すべきです。
不具合を予防するためにリフォームをすべきか
現時点では漏水は発生していないものの築年数的にそろそろ水道管の更生をすべきか判断する場合を考えてみましょう。
現時点では漏水は発生していないので、やってもやらなくても賃料や稼働率に差は出ません。一切収益は生みませんが、不幸にも入居中に不具合が発生した場合、水道管の修理費用だけではなく、床や壁の修繕、さらには入居者の仮住まいといった費用が掛かるかもしれません。
選択肢(1) 水道管更生工事を実施
費用:20万円
選択肢(2)-1 何もしない 漏水発生せず
費用:0円
選択肢(2)-2 何もしない 漏水発生
費用:50万円
誰だって(2)-1がいいに決まっていますし、(2)-2になるくらいなら(1)の方がいいですが、どうすればいいでしょう?
一つの考え方は、選択肢2−2が起こった時に費用負担ができないのであればそのリスクを取るべきではなく、予防工事を実施すべきというものです。
それであれば確かに最悪の事態を防ぐことはできます。
しかし、不動産賃貸業には無数のリスクがあります。
・物件にトラックが突っ込んでくるかも
・物件で殺人事件が起きるかも
・物件の外壁が落下して通行人に被害を与えるかも
・物件に飛行機が衝突するかも
どだい全てのリスクに備えることなんてできませんし、そんなことしていたら事業として成り立ちません。
不具合が発生した際の影響度(費用)が甚大ならリフォームせざるを得ないという訳ではなく、(保険等で合理的に対応できないか検討した上で)使用年数、徴候的事象から発生可能性を推測し、それをリスク発生時の影響度と掛け合わせてリスクレベルを算出し、リスクレベルが高いものはなるべく潰すという考え方が個人的には真っ当だと思います。
「リスクレベル=発生可能性×影響度」
発生可能性といっても厳密に〇%と測定できるわけではありませんが、例えば漏水で言えば、赤水とか水圧の低下といった徴候的事象が発生していて、なおかつ漏水が起きた場合に構造上多大な修理費用が掛かるような物件はリスクレベルが高いです。
逆に物件が平屋戸建で漏水が起きてもバイパスして簡単に直せるのであればリスクレベルは低いと言えるかもしれません。
相対的に優れた選択肢でももはや手遅れということも
このようにとりうる選択肢を全てシミュレーションして比較することを個人的におすすめしますが、
賃貸経営のある期間を切り取ってのシミュレーションになるので、どちらを選んでも投資全体で見るとさほど変わらないとか、どちらを選んでももはや全体での損失は回復できないということもあります。
全体として損している場合でもより損失を軽減するために比較には意義はありますが、
そんな苦渋の後ろ向きな決断をしなければならない日が来ることがないよう祈るというか、都度都度の事業判断を的確に行ってそんな日が来ることを避けていただければと思います。
shiro-shita
最新記事 by shiro-shita (全て見る)
- AIが賢くならない未来 - 2025年12月13日
- 不動産ポータルサイトでは伝えきれない物件の魅力をいかに伝えるか - 2025年12月4日
- 不動産会社に依頼した入居者募集が決まらないときにやること 不動産オーナーによる物件マーケティング戦略の検証その2 - 2025年11月27日